スタッフ紹介
-
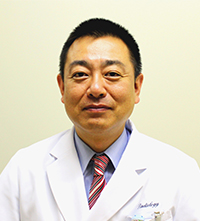
教授加藤 勝也Katsuya Kato
-
特任教授金澤 右Susumu Kanazawa
-
准教授藤原 寛康Hiroyasu Fujiwara
-
講師坪井 有加Yuka Tsuboi
-
講師福原 由子Yuko Fukuhara
-
講師小野 由美香Yumika Ono
教育重点及び概要
当教室は川崎医科大学総合医療センターを拠点としており、平成23年に新設された。現在は医大生の臨床実習と研修医の卒後教育を担っている。附属川崎病院は救急診療・癌診療に長く取り組んできた病院でcommon diseaseを学ぶのに適した病院である。放射線科では、医大生、研修医ともに高精細の画像端末を自ら操作し、CT・MRIなどの画像読影を学び、研修医はさらに実臨床での読影レポート作成を学ぶ。現在ティーチングファイルを充実させ、学習環境を整備している。また、IVR(interventional radiology)に力を入れており、悪性腫瘍の動注塞栓術、CTガイド下生検、ラジオ波凝固療法、各種ドレナージ、中心静脈ポート留置などの手技を学ぶ。医学生は時間の制約もあり、見学のみとなっているが、研修医は、手技に参加し、術前後の管理、患者へのインフォームドコンセントも含め、上級医と共にこれら全てを学ぶ。
- 自己評価と反省
-
平成23年に新設された教室であり、教育体制の構築途上であるが、まず医大生は、画像診断に関しては、現状ティーチングファイルを用いた読影検討のみとなっているが、学生の感想からは、実践的実習になっていると考えている。今後は、時間的な制約もあるが、症例を対比しながら系統立った画像診断実習としていくことが課題と考えている。なお平成26年度以降1ヶ月間の6年生臨床実習を2名受け入れ、この2名には時間をかけてある程度系統だった実習を行うことができた。今後もプログラムを改善しながら、継続していく予定である。IVRに関しては短期間の実習では見学型実習にならざるを得ず、参加型実習への段階的移行を模索中である。
次に研修医教育に関しては、これも現在構築途上であり、具体的な研修プログラム、評価項目の策定はまだ出来ていない。現状は、各研修医の希望を受け、各研修医の実習時の到達レベルも考慮しつつ、カスタマイズしつつ実習を行っている。今後は、研修プログラムや評価項目の具体化、可視化を進め、実習中の到達レベルを自己評価しつつ研修を行うことが出来るシステム構築を目指す。
研究分野及び主要研究テーマ
画像診断については、以下のようなテーマについて、主に多施設共同で研究を進めている。
- じん肺の診断基準及び手法に関する調査研究
- 胸膜中皮腫の的確な診断方法に関する研究─鑑別診断方法と症例収集─
- 胸膜中皮腫に対する新規治療法の臨床導入に関する研究
- 造影CT、拡散強調MR画像、FDG-PETによる非腫瘍性胸膜肥厚鑑別診断能の比較に関する前向き検討
- 石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務(びまん性胸膜肥厚に関する調査業務)
- 肺内石綿繊維計測精度管理等業務
IVRに関しては、以下のテーマがある。
- 血管腫・血管奇形患者の実態把握のための全国疫学調査
- 血管腫・血管奇形の硬化療法・塞栓術
- 永久塞栓ビーズを用いた動脈塞栓術
- 悪性腫瘍に対するラジオ波凝固療法
- 自己評価と反省
- 平成23年に新設された教室であり、研究体制を構築過程である。
研究分野及び主要研究テーマ
次年度に迫った附属総合医療センター開院へ向けより良い診療・教育・研究環境を作ることが最重点目標である。今後放射線医学教室(画像診断1)とも連携してスタッフの充実を図っていく。

